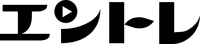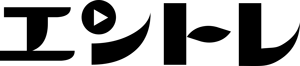織山尚大が挑む――衝撃の実話に基づく舞台『エクウス』観劇レビュー
実際の事件に着想を得た戯曲を、小川絵梨子による新訳・演出で上演する舞台『エクウス』は、2026年1月~2月に東京・東京グローブ座、大阪・サンケイホールブリーゼで上演中です。
 舞台『エクウス』撮影/宮川舞子
舞台『エクウス』撮影/宮川舞子
ピーター・シェーファーの戯曲『エクウス』は、表面的には異常犯罪を描きながら、人の心に潜む闇と激しい情熱をあぶり出す心理劇の傑作として知られています。厩舎で6頭の馬の目を突くという事件を起こした少年アラン・ストラング。その治療を任された精神科医ダイサートは、彼の内面に迫るうち、常軌を逸した信仰にも似た情熱の核心へと近づいていきます。
1973年にロンドンで初演され、“演劇史に残る衝撃作”と評価を獲得。1979年にはブロードウェイで上演され、トニー賞で多数部門にノミネート、最優秀作品賞を受賞しました。その後も世界各地で上演が重ねられ、1990年には劇団四季が日本初演。2007年のロンドン公演ではダニエル・ラドクリフが少年アラン役を務め、大きな話題となりました。
宗教に否定的な父と、アランを溺愛する敬虔なキリスト教徒の元教師の母。相反する思想のあいだで、アランは揺れながら育ちます。
幼い頃のある体験をきっかけに、彼の中で馬を神格化する観念が芽生え、やがてそれは信仰にも似た確信へと変わっていきます。崇拝と欲望――抑圧された感情が絡み合い、次第に異様な執着へと姿を変えていくのです。
そしてなぜ、彼は信仰する馬の目を突くという凄惨な事件を起こしてしまったのか。
事件の真相をたどるほどに、“異常”という言葉では片づけられない、人間の奥底に渦巻く葛藤と祈りがあらわになっていきます。
事件だけを見れば、あまりにも狂気的で残酷な出来事です。もちろん決して許される行為ではありません。けれど、その背景を丁寧にたどっていくと、単なる“異常”では片づけられない理由が浮かび上がってきます。アランの孤独や葛藤に触れるほどに、どこか寄り添い、胸が締めつけられるような思いを抱いてしまいました。
本作を観劇し、多様な価値観や家庭のかたちが存在する現代においても、決して遠い世界の物語ではないと感じました。少年犯罪が起こるたび、家庭環境や家族との関係性が取り沙汰されます。本作は、それらが人の心の形成にどれほど深く関わっているのかをあらためて考えさせます。特別な誰かの物語ではなく、私たちのすぐ隣にあるかもしれない現実を、静かに突きつけてくる作品です。
 舞台『エクウス』撮影/宮川舞子
舞台『エクウス』撮影/宮川舞子
主人公アランは、印刷屋を営む父から「テレビを見るのは禁止だ。印刷屋の息子なら本を読め」と言われ、テレビを取り上げられます。けれど、子どもは生まれる家庭を選べません。父は「乗馬は上流階級のならず者がやること」と決めつけ、アランが初めて馬にまたがり高揚感を味わった瞬間さえも否定してしまいます。危ないからと無理に降ろされそうになり、落馬する場面は、芽生えた関心が断ち切られる象徴のようにも映りました。
一方、母は寝る前に聖書を読み聞かせます。それもすべて、息子を思い「良かれと思って」続けていることです。宗教そのものを否定も肯定もしませんが、その教えが幼い心にどのように積み重なっていくのかを思うと、簡単には割り切れない根深さを感じます。
宗教観も価値観も異なる両親ですが、「子どものため」という思いの強さという点では、どこか似ているようにも映ります。善意であるはずの言葉や行動が、いつの間にか子どもの自由を狭め、心の逃げ場を奪っていく。そこに当事者の自覚はありません。
また、“性”も本作において重要な要素です。母は、生物的にも精神的にも大切なこととして、宗教観を交えながらアランに語りかけます。しかしそれは母の視点からの教えであり、アラン自身の戸惑いや実感に寄り添う形ではなかったのかもしれません。その結果、信仰と結びついた罪の意識が残り、やや偏った性の捉え方へとつながっていったようにも感じました。家庭や教育機関での正しい知識の普及が、青少年の心身を守ることに繋がるのではないかと考えさせられます。
さらに、両親は価値観の違いからたびたび衝突し、激しい口論を重ねます。近年では、子どもの前で繰り返される夫婦喧嘩も「面前DV」とされ、心理的虐待の一つと捉えられるようになりました。直接手を上げなくとも、その緊張や恐怖は確実に子どもの心に影を落とします。
難しいのは、両親ともに息子を愛しているという点です。どちらも「息子のため」を思い、その信念ゆえにぶつかってしまう。けれど、その衝突の只中に立たされる子どもにとっては、愛情と同時に不安や混乱も降りかかります。
善意と愛情があるからこそ、問題は単純ではない。どこまでが守ることで、どこからが縛ることなのか。本作はその境界線を静かに問いかけているように感じました。
舞台上に置かれているのは木のベンチのみ。装置は極めてシンプルで無機質、大きな舞台転換もありません。そのぶん、ごまかしがきかず、空間を満たすのはキャストの声と存在感そのもの。演技力がすべてと言っても過言ではない、研ぎ澄まされた構成でした。
 舞台『エクウス』撮影/宮川舞子
舞台『エクウス』撮影/宮川舞子
主人公アランを演じる織山尚大さん。幼少期から培ってきたダンスで磨かれた表現力には定評があります。織山さんが放つ少年と大人の狭間にいる青年期ならではの美しさ。透き通るような透明感と、揺らぎ。危うさとミステリアスな気配をまとう姿から目が離せず、作品へどんどん引き込まれていきました。純粋さと狂気が同居するアランという難役を、感情だけに頼らず、繊細な身体と言葉で立ち上げていきます。
目を潤ませ、膝を抱えてうずくまる姿はピュアで、触れれば壊れてしまいそうな儚さがあります。言葉を閉ざし、静寂の中に沈む時間から、一転して胸の奥の思いを激しく吐露し、感情を爆発させる瞬間へ――その振り幅の大きさに息をのみます。
感情の起伏が絶えず揺れ動き、精神的にも過酷な場面が続く役どころ。それでも一つひとつの瞬間を丁寧に表現する姿が印象的でした。光を受けた横顔の美しさは、ときに少年のように無垢で、ときに追い詰められた影を宿し、強く心に残ります。
母が面会に訪れた際、アランは冷たいまなざしで彼女をにらみつけます。その視線に耐えきれず、思わずひっぱたいてしまう――緊迫した場面です。騒ぎとなり、医師から「もう二度と来ないでください」と告げられると、母は強い口調で言い返します。
「あなた方はすぐ親のせいにするけれど、私たちは息子を愛し、大切に育ててきた。後悔することなど何一つない。子どもは一人の独立した人間で、彼の中に悪魔が入ったのだ」と。
彼女にとって、息子の犯した罪はあくまで本人の問題であり、その背景に自分たちの影響があるとは思っていません。むしろ、自らの行いを正しいと固く信じています。
そこにあるのは、揺るぎない確信と、決して崩れない自己正当化。愛してきたという自負があるからこそ、自らを疑うことができない。その姿は責任転嫁というよりも、信念の強さゆえの盲目さのようにも映ります。
“信じる”ことは光にもなるが影にもなる――その危うさが、痛いほど浮かび上がる場面だと感じました。
 舞台『エクウス』撮影/宮川舞子
舞台『エクウス』撮影/宮川舞子
アランの治療に当たる精神科医ダイサートを村川絵梨さんが演じます。
これまでドラマで拝見する機会が多く、どちらかといえば柔らかな印象を抱いていましたが、今作では新たな挑戦をされています。従来は中年男性が演じることの多い役どころを、女性設定で体現されている点は驚かされました。しかも、ご本人いわく、演劇人生で最も台詞量の多い役とのこと。観ているこちらまで息が詰まるような、怒涛の台詞の波――。それでも毅然とした佇まいで淡々と語る姿からは、揺るぎない覚悟がにじみました。
アランは、ときにダイサートの脆弱な部分を鋭く突いてきます。関わりを深めるほどに、ダイサートは彼を“治療する側”でありながら、次第に自分自身を見つめ直さざるを得なくなっていきます。
アランは注射や投薬によって徐々に“治療”され、衝動は抑え込まれていきます。しかしその過程に、ダイサートは強い葛藤を抱きます。
「崇拝を奪うこと以上に残酷なことはない。崇拝こそが核だ」と。
生きる苦しみや痛みの中で、彼を支えてきたのは“崇拝”という激しい情熱でした。それがあったからこそ、孤独の中でも生きていられた。もしそれを取り去ってしまえば、彼の内側には何が残るのか――ダイサートは、その先に待つ空虚を恐れます。
痛みを伴いながらも、自分の人生に確かな情熱を持つアラン。その純度の高さに、ダイサートはやがて羨望さえ覚えるようになります。そして同時に、自らを省みるのです。
自分は安全な理性の内側に身を置き、傷つくことを恐れて、何も燃やしてこなかったのではないか、と。“正常”に生きることと、“激しく生きる”こと。どちらが本当に幸福なのか――その問いを、本作は突きつけてきます。
第一幕後半、ついにアランと馬の“秘密”が明かされます。
彼は馬と一つになりたいという強烈な衝動に突き動かされ、驚くべき行動に出るのです。馬の身体表現や馬と一体化し悦びに浸る姿は、生々しいほどの興奮とリアルさがありました。
取材会で織山さんは「アランに似た部分を自分にも感じていて、共感するところがあります。彼はものすごく病んでいますが、僕も病んでいるので……(笑)」と語っていました。その言葉には冗談めかした響きがありつつも、役と真摯に向き合っていることが伝わってきました。
実際、あの繊細さと振れ幅の大きい感情を体現するには、自身の内側を深く掘り下げる覚悟が必要なのだろうと思わされます。それほどまでに、アランという役は心身ともに消耗する難役でした。
役作りとして、朝はスープだけにして“やせ細った男の子”の佇まいを作ったというエピソードからも、その本気度がうかがえます。外見だけでなく、内面から削ぎ落としていくようなアプローチ。だからこそ、舞台上のアランには現実味と切実さが宿っていたのだと感じました。
アランを乗馬クラブの仕事へ導き、事件の引き金となるジル・メイソン役を岡本玲さんが演じます。実年齢は織山さんと一回り近く離れているとは思えないほど、弾ける笑顔とキュートな佇まいで、年の差を感じさせません。明るくリードする少し年上のお姉さん役がよく似合っていました。ジルは少し押しの強い一面を持ちながらも、無邪気さを感じさせる人物。その無邪気さゆえの行動が、結果として後の悲劇にも繋がります。
岡本さんの演技はこれまでドラマや舞台で何度か拝見していますが、安定感があり、物語の中に溶け込む自然さを感じます。
 舞台『エクウス』撮影/宮川舞子
舞台『エクウス』撮影/宮川舞子
須賀貴匡さんは、『仮面ライダー龍騎』の印象が今も鮮やかですが、端正な顔立ちとどこか気高さを帯びた佇まいは、騎馬の若者役、そしてアランが憧れる馬という存在そのものを体現する役どころにぴたりと重なっていました。
アランが初めて馬に心を寄せるきっかけとなる存在であり、彼が情熱や愛情を惜しみなく注ぐ対象として、強い説得力を放っていました。
第二幕で、物語が大きく動きます。ジルに誘われて行ったポルノ映画館で父と鉢合わせします。その瞬間、アランの中で何かが崩れ落ちます。威厳をまとい、正しさを語ってきた父もまた、欲望を抱える一人の俗な人間だと気づくのです。その事実は、抑圧してきた父への嫌悪や軽蔑へと反転します。「あいつはかわいそうな親父だ」と吐き捨てる言葉の裏には、裏切られたような気持も滲んでいるようでした。親の性的な部分を見たくない――それは多くの人が抱く自然な感情ではないでしょうか。どれほど紳士然と振る舞っていても、人は誰しも自分だけの秘密をを抱えている。絶対的だった父の偶像が崩れる場面を目撃してしまったのです。そこには、父へ入り混じった、ある種のファザー・コンプレックスも感じられました。
その後、ジルに連れられ厩舎で二人は過ごすことになりますが、アランにとって厩舎は神殿であり、馬は神。“いやらしいこと”は汚れであり、罪と感じていたのではないでしょうか。また、愛する馬とはエクスタシーを感じられたのに、現実の女性を前にするとできない。信仰する神に見られているような感覚に襲われ、そんなみっともない姿を見られたことに対する強烈な羞恥心、絶望――色んな気持ちに耐え兼ね、追い詰められてしまったことが推測されます。
クライマックスで、アランを治療することは「普通の人間に戻す」行為であり、それは彼から情熱を奪うことではないのか。という想いが更にダイサートにこみ上げます。心酔し、崇拝するほど特別だった馬という存在。“情熱は破壊できても、意図して創り出すことはできない”――その言葉の重みを感じます。最後にダイサートが「あなたを治すから」という一言には、救いと同時に、何かを切り取る響きも含まれているようでした。アランが“普通”になることは、彼の核が無くなることでもあるのではないか、と。
昔から存在していた現象かもしれませんが、近年の日本では「推し活」という言葉が広まり、誰もが“自分だけの推し”を持つ時代とも言われます。熱烈に崇め、人生の中心に据える人もいます。愛や信仰心は、大きなエネルギーとなり、ときに社会を動かすほどのムーブメントを生み出します。けれどその歯車がわずかに狂ったとき、盲目的な熱狂は崩壊へと向かうこともあるのです。
『エクウス』は、愛や信仰が人を救いも殺しもする、その事実を考えさせる作品だと感じました。
今作は、織山さんにとって多くの事務所の先輩・後輩たちが舞台に立ってきた東京グローブ座での初主演公演。この場所に立ち、「やっとこの景色を見られた。こんな景色だったんだ」と語った言葉からは、胸に込み上げる思いがまっすぐに伝わってきました。グローブ座は奥行きのある広い舞台で、客席との距離が近く感じられる劇場です。特に2階席は舞台全体を見渡しやすく、俯瞰で芝居を味わえるのが魅力です。
織山さんが寝そべったり、客席を見渡したり、天井を見上げたりする場面も多いため、その角度だからこそ見える表情があります。ふとした瞬間の美しい寝顔を堪能できるのは、もしかすると2階席ならではの特権かもしれません(笑)。
公演は東京だけでなく、後半には大阪公演も控えていますのでお楽しみに。
取材会で「主人公アランのように、いま激しく情熱を感じているものはありますか?」と問われると、織山さん含め、キャストは一堂に「今は、この作品ですね!」との返答。実際に皆さんで、馬に乗りに行き、触れ、ブラッシングも体験されたそうです。眼に吸い込まれるような感覚、言葉にならないのに確かに伝わる何か。迫力とぬくもり、匂い、そしてどこか神秘的な気配――その実感が、舞台上の説得力へとつながっていることを感じました。
全キャストが情熱を注いで挑む舞台『エクウス』ぜひ劇場でご体感ください!
(文:あかね渉)
舞台『エクウス』
作:ピーター・シェーファー
翻訳・演出:小川絵梨子
キャスト
織山尚大 / 村川絵梨 / 岡本玲 / 須賀貴匡 / 近藤隼 / 津田真澄 / 坂田聡 / 長野里美 / 千葉哲也
【開催日程・会場】
2026年1月29日(木)〜2月15日(日)
東京都 東京グローブ座
2026年2月20日(金)〜24日(火)
大阪府 サンケイホールブリーゼ