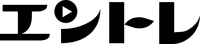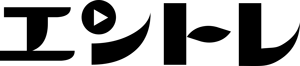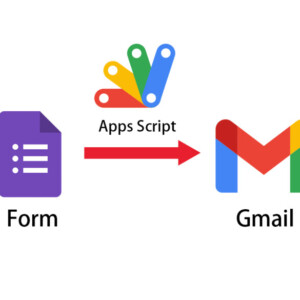![[演技術考 I ] 演技とは何か? 〜その“曖昧さ”における功罪について〜](https://entre-news.jp/wp-content/uploads/2021/12/engijutsu-ko-1.jpg)
[演技術考 I ] 演技とは何か? 〜その“曖昧さ”における功罪について〜
![[演技術考 I ] 演技とは何か? 〜その“曖昧さ”における功罪について〜](https://entre-news.jp/wp-content/uploads/2021/12/engijutsu-ko-1.jpg)
[演技術考 I ] 演技とは何か? 〜その“曖昧さ”における功罪について〜
[演技術考 I ] 演技とは何か? 〜その“曖昧さ”における功罪について〜
今回は、現在の“演技”を取り巻く状況について、技術ないしは技術教育という観点から考えてみたい。
・・・とは書いてみたものの、何らかの正解といった様なものを期待されては甚だ困ってしまう。音楽や演劇に関しての“物理的な領域に属する技術”を文章で言い尽くすことはまず不可能と言ってよい。いくら頭をこねくり回してそれっぽいことを書いたところで、少なくともそれを読んだ人の演技力がたちまち向上するとか、そういった即効性のある実益はまず期待できない。だが、あえて演技などという雲を掴む様な曖昧な対象について、改めて考え直してみることにはそれなりの意味も存在している様に思われてならないのだ。
そこで、とりあえず演技の良し悪し、すなわち演技の“上手い” “下手”とは一体どういったことなのか? という問題について考えてみることから始めたい・・・が、しかし実のところ、これがまた難しく一筋縄では行かない。というのも、社会的機能という点からみれば、演技を“上手いと感じる”か“下手と感じる”のかは受け手(鑑賞者)の感覚に依存する部分が多く、それ故にその良し悪しについても、結局のところ“好みの問題”に終始してしまうことが多いように思われるからだ。
もちろん、セリフを忘れてしまう、声が小さ過ぎて聞こえない、なまりが強すぎて何を言っているのか理解出来ない、明らかな棒読み等、台詞表現にあからさまな障害が見られる場合は迷うことなく“下手くそ”と判断されるので話は早いのだが、まあ、最近の人でそこまで極端に感の悪い人というのもそう多くは見当たらない。こうなると却って“上手い” “下手”を断定することは余計に難しい。
もちろん、特定の劇団における特定のスタイルを基準とし、その基準からの逸脱具合を持って“下手”の度合い、ないしは優劣を決めることは可能だろうが、それはあくまでも特定の劇団に特有の表現における“上手い” “下手” であって、それが伝統のある有名劇団だとしても、それをもって客観的とし、演技の“上手い” “下手”を判断することは出来ないのだ。
私の父がかつて劇団民藝の制作をしていた関係で、当時のスクラップブックが残っている。新聞の文化欄、主に劇評の切り抜きだ。その中でも特に印象的なものがある。民藝のある公演についてのもので、有馬稲子さんの演技に対してなかなか辛辣な内容となっている。
「映画スター有馬稲子を起用したのは(中略)この実験は客を呼ぶ可能性以外は失敗だったようである。」
それにしても近年、こんなに忖度の無い批評にはまずお目にかかる機会がないので、それ自体にちょっと感動してしまったりもするのだが・・・。まあ、それはさておき、有馬さんと言えば、宝塚歌劇団の中でも自他共に認める超美形の娘役として名を馳せ、当時すでに銀幕のスターとしても確固たる名声を築かれていた。その後、そうした華麗なるキャリアをお持ちにも関わらず改めて民藝に入団された訳だが、これはその頃の劇評。余談だが、当時、父が語ったところによると「あんな大スターなのに、「新入りだから」って誰よりも早く稽古場に来て掃除してる。偉いよ。」だそうな。往年のタカラジェンヌらしいエピソードだ。
それはともかく、ここで注目すべきは宝塚の娘役として活躍された有馬さんの演技が新劇(少なくともこの作品における劇評)ではコテンパンだったという点。もちろん、どちらの劇団のレベルが高いか低いかの話ではない。それに、そうした比較はナンセンス極まりない。要するに、私が言いたいのは、 作品や演出(求められる表現)の傾向に則して、演技の手法(客観的に解釈可能な根拠を有する技術)を選択できればそれに越したことはないのではないか? ということに尽きる。ちなみに、他の劇評(同作品)では有馬さんを絶賛していたことを付け加えておきたい。
「女優陣が好演。新劇初出演の有馬は、舞台に精彩を添えたというだけでなく、けんめいに演じて期待を受けとめた。」
そこで、こうした事実から考えられる可能性は?
① 否定派が正しく、絶賛派が忖度している。
② 否定派がへそ曲がりで、絶賛派が正しく批評している。
③ 両批評家の観劇日が異なり、芝居の出来が両日で異なっていた。
④ 批評家ごとの好みの問題。はっきり言って“好き嫌い”の問題。
どれが正解かは藪の中。今となっては確かめる術が無い。
ただ、ここから一つ言えることは、②と④は仕方がない。「ほっとけ!」「好きに言わせておけ!」という話。この場合、役者に非は無い。だが、①と③は役者自身である程度コントロールできる部分なので、ここはなんとかしておきたい部分ではある。この“コントロールできる”ということこそが“技術”であり、延いては“演技術”ということになる訳である。
そこでもう一度。
作品や演出(求められる表現)の傾向に則して、演技の手法(客観的に解釈可能な根拠を有する技術)を選択できればそれに越したことはないのではないか?
そして「やるべきことをちゃんとやって、それでもダメなら気にするな。きっと何処かに君の演技が好きな人もいるよ。脇目も振らずに日々精進!」となる訳である。だが、そもそもそんな最大公約数的な演技手法なるものが存在するのかという問題もある。よしんば、そんな手法が存在したとして、何処に行けばそんな妙技を会得できるというのか?
演劇科や各種専門学校、劇団の類はあまた存在するものの、私が知る範囲でその“指導”、ないしはその指針についての考察を試みるならば、それらは客観的な技術指導というよりは、指導者の趣味や個人的経験(経歴)、“劇団内で共有されているルール”によるところが大きい様に思われてならない。一言断っておくと、ここでは単にそれを批判しようとしている訳ではない。そうした個別の経験(経歴)が各人の個性というフィルターを通すことで、いわば変異種を生み出す様な形でそれぞれの俳優の個性(オリジナル)が生まれるという側面も決して否定できないからだ。それに古今東西、そもそも“客観的な演技の技術”なるものが確立されているとは言い難い。そこが音楽(※ここでは西洋音楽を指す。以下、音楽。)と大きく違うところだ。
音楽の場合、音楽を理解する上での指針となる技術の蓄積がまとまった形で既に存在する。しかもほぼ万国共通。和声学、対位法、管弦楽法etc. 演奏技法に関しても大枠では万国共通だ。例えばピアノで音階(ドレミファソラシド)を右手で弾く場合、親指から始めて、“ファ”で再び親指を使う。こうした類の演奏の基本は確立していると言ってよい。これらは、音響という物理的な側面と人間の肉体構造の妥協点を上手いこと見出し、それを高度なレベルにまで高めていき構造化したものだ。
だが、そこでは日本の伝統芸能に多く見られるような“間”といった微妙な表現や、音程を微妙に上下させて情感を表すような繊細な表現手法は、休符や平均律、ハーモニーといった合理的な方法をもって淘汰されてしまう。“合理的”などと言うと、あたかもその方が優れているように思われなくもないが、必ずしもそうとは限らない。民族音楽学者の故・小泉文夫氏は、むしろそうした西洋的傾向を、“わずか数百年の間に未開人から高度成長した民族の特徴”であるとし、古くから文明社会であった日本(中国、インドもだが)の方が大きなスパンで考えれば音楽の先進国なのだという。
ざっくり説明(“音階”を例として)すれば、西洋の七音音階では一つの音を高めたり低めたりといったデリケートな使い方はせず、「このスイッチ(鍵盤)押したら“ド”で、隣の黒いスイッチ(鍵盤)押したら“#ド”ね。これが半音だよ。」といった具合に、スイッチ(鍵盤)とスイッチ(鍵盤)の間にはまるで音が存在しないかの如く振る舞う単純なシステムを採用(注釈)・・・これはハーモニーの存在が維持された世界においては、あらかじめメロディで使う音をかっちり決めておく必要があることに由来。これに対し、日本の五音音階は七音より数が少なくテトラコルド(※一般的なギリシャ由来のそれではなく、小泉氏が定義したテトラコルド)に中間音が一個しかない分、その中間音の音程変化を作品の情緒表現に応じて実に巧みに使うのだという。確かにそうした観点に立てば、西洋と比較して私たちの音楽文化は“よりデリケートな表現を有する”と言えなくもない。
まあ、西洋と東洋の音楽における優劣の問題はさておき、話を戻せば、西洋音楽における万国共通のルールに基づいた技術の蓄積、その利点(芸術表現というコミュニケーションにおける利点)は、共有済みのルール・技術を持ってして作品ごと(共有されたルール・技術を駆使して生み出された、各作曲家の個性や楽曲のスタイル)に各人が適切と思われる表現方法(技術)を選択し、自らの解釈(根拠を持った表現)に努めることができるという点にあるのは間違いないが、そうした共有されたルールの有無は、“演技術”を考える上で大いに示唆を与えるところだろう。
話は大きく音楽に傾いてしまったが、要するにここで何が言いたかったかといえば、あくまでも音楽と比較しての話ではあるが、演劇の確立されていない部分、すなわち演劇の“曖昧さ”が必ずしも作品創造にとってマイナスになるとは限らないという点が1つ。だが同時に、この“曖昧さ”故の弊害が大きい様に思われるのもまた事実という点だ。さて、こうした文脈を踏まえた上で、改めて私が実際に目の当たりにしてきたよくある話、すなわち“机上”から“稽古場”に視線を移して考えてみたいと思う。
学校の専門課程(演劇)を経てやってくる人たち(俳優志望者)の多くが、いわゆる形芝居(それも、お世辞にも“お上手”とは言えない)に終始する傾向にあり、もっと酷いのになると精神論とも呼べない精神論を口にしたりするもんだから始末に追えない。
「気分が・・・」
「まだ役の気持ちになりきれていないんです・・・」
「気持ちよく演じたい!」
「気持ちはお客様に伝わるものなので元気と笑顔で!」
これでは一体、何を勉強してきたのやら。そのくせ「演劇で食って行きたいんです!」と商売っ気だけは逞しい。
まあ、お金の話はさておき、そもそも中学・高校演劇等の情操教育(という演劇の側面)と専門家を育成する専門教育とは別物だと思うのだが・・・。
果たしてこれは生徒だけの問題なのだろうか?
では、教育者の問題?
それとも社会の問題?
いつしか“感性”という言葉は一人歩きし、芸術文化の免罪符の様に思われている節があるが、そうしたある種の社会的機能を有する気分とでも言った様なものが、却って真実を隠蔽する装置として機能している様に思えてならないのは私だけだろうか? よく「私は演劇とか音楽とか・・・そういうのはよく分からないので」と謙虚を装いつつの無関心を標榜する御人にお目にかかるが、“感性”という名の免罪符とはそのような無関心と表裏一体の様に思えてならないのだ。
芸術(主に演劇と音楽)における専門的技術と社会との関係については私自身、大学院の頃からの主要な研究テーマの一つでもあり、今まで色々と考察したりなんかもして来た訳なのだが、訓練された技術を有した(演劇の場合、これ自体かなり微妙な問題だが)専門家が創り、訓練された技術を持たない非専門家によって鑑賞される運命にあるといった演劇、ないしは音楽作品の性質上、専門的技術(の軸)と社会(の軸)とが交差する地点を見出すとともに、客観的かつ妥当性を有するレベルの論理を展開するのはそう簡単な話ではない。だから、どうしても比較を通したケースごとの小さな結論を如何に導き出すかといったゲーム、学問の為の学問になりがちなのは否めない。
そこで初心に帰ってみようと思う。
で、どうするかと言えば、次回「演技術考II」では、歴史を遡ってこうした問題を考察してみたい。現代的な意味での“現代劇”の誕生に立ち会って(タイムスリップして)みたいと思う。
その6 》[演技術考 II ] 新劇の誕生 〜踏路社の演技術に見る演劇と音楽の互換性〜
(文:関口純 ※文章・写真の無断転載を禁じます)